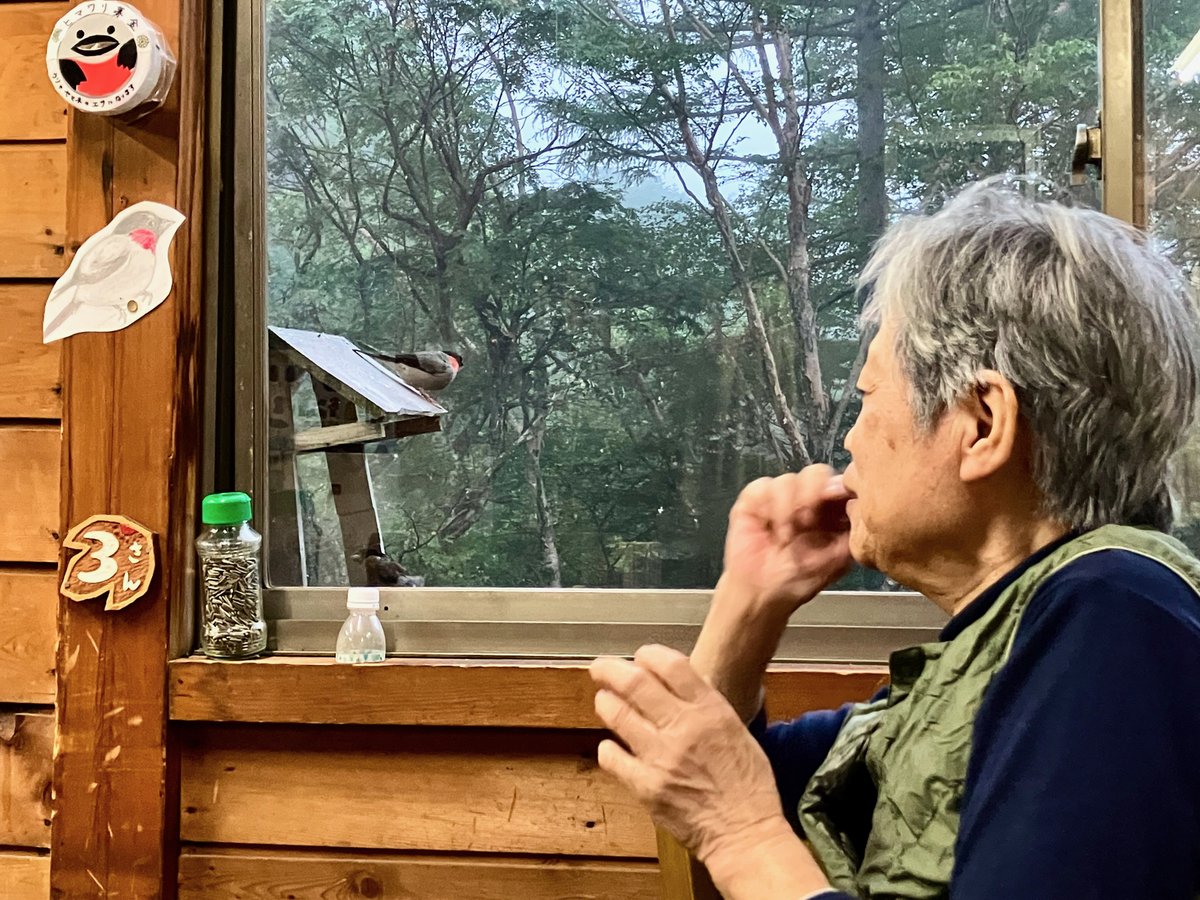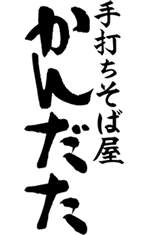コインロッカーの使い方がよくわからない。
支払いスペースの横に、
細かい字が書いてあるのだが、
天井の照明で光ってよく読めない。
反対側では、スカーフを髪にかけた、
アジア系の女性が、英語で書かれた、
説明書を読んでいる。
どうやら、緑色のランプのついたロッカーに、
荷物を入れて、それから、
この機械で手続きをするらしい。
で、緑色のランプのロッカーはと探せば、
ああ、かのスカーフの女性が、
小型のスーツケースを入れるところではないか。
あとは、全て、赤ランプ。
一番下の、大型トランク用のロッカーが空いていたと思ったら、
すぐに、埋まってしまう。
新宿駅の南口にある、
高速バスターミナル。
100個以上はあると思われるコインロッカーは、
全て使用中。
大型のスーツケースを脇において、
空くのを待っている外国人もいる。
そこを諦めて、
甲州街道ガード下のコインロッカーへ。
荷物を預けると、
出てくるのは、鍵ではなく、
何やら模様の入ったレシート。
出す時には、この模様を、
どこかに押し付けるらしい。
まったく、時代の変化に付いていけない。
旅に出ると、
世の中のシステムが、
大きく変わっていることを実感する。
高速バスのチケットは、
携帯電話に送られてきて、
その画面を示すだけ。
電車の切符は、
予約しておいた乗車券を、
機械で受け取る。
その紙の切符で改札を通ろうとしたら、
あれっ、入れる穴がない。
なんと、IC専用の改札機だって。
特急券は、やはり、携帯の画面に。
ホームで売店で、
飲み物を買おうとしたら、
無人のキャッシュレス専用レジ。
普段から、使っている方だったら、
なんの不便もないのだろうが、
何年かぶりに東京に出てくる身としては、
戸惑うばかり。
伊東からの帰り道。
ほかに用事のある女将と別れ、
高速バスの発車までの三時間弱を、
この新宿の街を一人で歩いて過ごす。
二十代前半まで、東京で暮らした私にとって、
新宿は懐かしい街だ。
だいたい、コインロッカーのある、
甲州街道のガード下の景色が違う。
今もあるはずなのだが、
このあたりは、馬のファンが集まるところで、
土日などは、大騒ぎだった。
そういう人を目当ての屋台が並んでいたっけ。
そこから入る武蔵野通りも、
まったく、違う風景。
大型の量販店と、さまざまな飲食店。
とにかく、夕方間近の時間だというのに、
歩く人が多い。
あれ、映画館、武蔵野館の大看板はどこへいったの。
それでも、懐かしい店、
ビアホールの銀座ライオンは健在。
突き当たって、新宿通りに出れば、
正面が紀伊國屋書店。
そして、左に曲がれば、
新宿中村屋、その先に高野フルーツパーラー。
この辺は変わらないね。
でも、あまりの人混みに、
やや、混乱気味。
静かな場所を求めて、
中村屋のビルに入って、
中村屋サロンへ。
入場料300円。
それで喧騒から離れた、
小さな、小さな、美術館へ。
新宿中村屋を始めた相馬愛蔵は、
長野県の安曇野の出身。
最初はパン屋だった中村屋を、
少しづつ大きくしながら、
しっかりとしたブランドに育てたのだね。
そして、多くの芸術家と交わり、
時に援助し、助けられたりしたのだ。
特に、彫刻家の萩原禄山(ろくざん)とは親交が深かった。
その話は、いくつかの小説の題材にもなっている。
そして、その禄山の代表作、
「女」が展示されていた。
それだけは写真を撮っていいというので一枚。
実は禄山は、相馬愛蔵の妻、国光(こっこう)に、
想いを寄せていたという。
安曇野には、禄山の美術館があるが、
若い時に訪れてから、この話を知った。

サロンには、歌人でもあった、
会津八一の書があった。
中村屋の羊羹の上書きをしたのだ。
棟方志功が描いた包み紙もあった。
これだけの人混みの中から、
ほかに来る人もなく、たった一人で過ごしたサロン。
エレベーターを降りて、再び人混みの中へ。
このギャップはなんだ。
東口の広場に出れば、
大勢の人が、斜め上を見上げている。
アルタビルの大きな映像を見ているのかと思ったら、
その向こうに、大きな猫の映像が。
なんじゃこりゃ。
話には聞いていたが、
なかなかリアル感があって、
はっきりと見える。
リアルと言いながら、
本物の猫とは違う存在感があり、
よく作られている。
すごいなあ、
新宿という街は。
常に、新しいことに、
挑戦し続ける街なのだ。

私が、紅顔の中学生だった頃まで、
ここから歌舞伎町方面に抜けた靖国通りには、
まだ、都電が走っていた。
東口の広場では、
裾の開いたジーンズを履いた、
長髪の若者たちが、
虚な目をしてシンナーを吸っていた。
西口では、
週末になると、反戦フォークソングの集会が、
自然発生的に広まり、
やがて、それを規制する機動隊と、
鬼ごっこをしていたっけ。
少しづつ、時代が動いて、
文化的な運動が盛んになった。
唐十郎は、神社の境内に赤テントを張って、
新しい芝居を始めた。
寺山修司も、劇場を離れ、
この街の路上を舞台に演じたものだ。
紀伊國屋の裏のジャズスポットで、
渡辺貞夫や日野皓正が熱い音を吐き、
歌舞伎町のカントリーバーでは、
ジミー時田やマイク真木が渋い声を聴かせた。
新宿文化劇場(のちのアートシアター)では、
先鋭的な映画が上映されていたし、
その横のミニシアターでは、
浅川マキが、あのしゃがれ声で歌っていた。
寄席の末廣亭では、
彦六(八代目林家正蔵)が、
か細い声で話し始め、
やがて、場内を圧倒していた。
アルタだって、
そこは二幸という、
食料品店のビルだったのだ。
えっ、知らない。
そうだろうねえ。
悔しかったら、70まで生きてみるとわかるよ。
記憶がだいぶ曖昧になっているけれど。
東口から、西口への地下道を通れば、
そこは、相変わらず、
ホームレスの方々の居場所。
西口に出て、ガード沿いに歩けば、
えっ、「思い出横丁」だって。
そんな名前で、
誰も呼ばなかったなあ。

若い時に、よく通った店は健在。
まだ、午後4時台だというのに、
酒を飲む人たちで、
八割がたが埋まっている。
いくつかの背中をすり抜けて、
奥まった席へ。
隣の中年の二人のサラリーマンたちは、
すでに、出来上がっていて楽しそう。
逆の隣の、初老の紳士は、
こちらをチラチラとみて、
話しかけたがっていた様子だが、
私は、ノスタルジーに浸りたいのだ、
放っておいてくれ。
金もない、二十台前半の頃、
よく、この店で過ごしたものだ。
今でも、まだ苦手な、酒を飲みながらね。
でも、見渡してみれば、
島になったカウンターを囲んでいるのは、
ほとんどが、中年以降の年齢の方。
長く店を続けているということは、
それぞれの思い出を抱え込んでいるのだ。
この店が、
ある映画のワンシーンに映ったことがある。
ブラッドピットや役所広司の出る映画で、
ちょっと大切な気分を表現する場面だった。
映画館で見た時、
すぐ、この店だとピンときた。
それ以降も、内装も、外見も変わらずに、
そして、スタイルも変わらずに、
商売を続けているのだ。
すごいなあ。
高速バスの時間もあるので、
思いを切り捨てて、席を立つ。
横丁を歩けば、
派手な飾り付けをした店もある。
外国人が、かなり入り込んでいる。
昔からそうなのだが、
この横丁には、
だいぶ怪しい、いや、
値段の不確かな店もある。
ここは、スマホでは検索できない世界。
そういう店に、大当たりするのも、
横丁歩きの、醍醐味なのだ、、。

西口の広場に出てみれば、
見慣れた小田急デパートの建物がなくなっている。
こらから、数年にかけて、
西口一体は、
大規模な再開発が行われるらしい。
街は、私があくびをして、
ボケーとしている間に、
どんどんと変わっていくのだ。
考えてみたら、この西口だって、
柵に囲まれた草原だった。
それが、栄養の悪いタケノコのように、
ニョキニョキと、高いビルが、
空に向かって聳えていったのだ。
人は、四角四面のビルの中だけでは、
生きられないのだろうなあ。
高いビルは、深い影を作り、
隠れたところに、
雑多な交わりの場所を育む。
そういう雑然とした世界の中で、
新しい考え方や文化も、
生まれてくることだろう。
だから、この街、
新宿は魅力的なのだね。
私も、たまには、
足を運ぶように心がけよう。
硬くなり始めた頭を、
解きほぐすようにね。