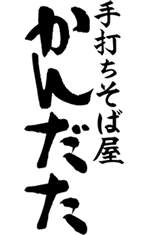私たちがスペインに行ったのは、
一月の中旬から下旬。
その頃のスペインでは、
コロナウイルスの話なんぞなかった。
折しも、中国の正月休暇にあたるというので、
首都のマドリードには、
たくさんの中国人が訪れていた。
まだまだ、渡航制限の無かった頃だものね。
私たちが、日本に帰ってから数日で、
中国からのそれが始まった。
既に、イタリアでの感染がニュースになっていたが、
スペインでは、対岸の火事という様子だった様だ。
それが、三月になって、
スペインでの感染者が急激に増え、
今では、医療が間に合わない様な事態になっている。
それを考えれば、
いい時に行ってきたものだ。
日本国内だって、
これからの感染拡大が心配されるところ。
そんな不安な空気の中では、
人の集まるところは敬遠され、
飲食店は、客足が遠のいている。
かんだた、もね。
かなり、、、。
こういう時は、お腹の空かない様に、
動かないでじっとしていよう。
で、しつこくスペインの話。
スペインで食べるところは、レストランの他に、
バルという店があって、
これがなかなか便利なのだ。
入ってみると、長いカウンターがあって、
そこで、立ったまま一杯いただくわけだ。
カウンターのケースに盛られた料理を、
おつまみとして注文することもできる。
立ったまま、食べたり飲んだりするのは、
我々には抵抗があるかもしれないが、
スペイン人は平気。
立ったまま、おしゃべりに興じている人ばかり。
時間帯によっては、どこも、
人で溢れていたりする。
もちろん、椅子の席もあるのだが、
数が少なく、人気店では大抵埋まっている。
マドリードのバルでは、
飲み物を頼むと、
結構なおつまみが付いてくる店もある。
長居はせずに、
そんなバルを何軒か回れば、
しっかりと夕食がわりになるのだ。
そして注目するのは、
そこで働くカマレロ(女性の場合はカマレラ)たちなのだ。
つまり、スタッフたち。
実にキビキビとよく動く。
あるバルなんぞ、女性一人で、
次々と来るお客をこなしていた。
我々の勘定をお願いすると、
きちんと正確に持ってくる。
大したものだなあ。
だけど、バルを使う客の方にも、
一つのルールがある。
それは、彼らのやりかけている仕事の、
邪魔をしないことだ。
声をかけたり、大袈裟に手を振ったりしないこと。
そんなことをすると、
永遠に無視されることになりかねない。
静かに待っていれば、
仕事の区切りをつけた彼らが、
顔を向ける。
その時に話すなり、ジェスチャーで示せばいい。
そういうタイミングを図ることが大切なのだ。
そんなところが、日本の居酒屋と違うところ。
だから、大勢の店内でも、
とても静かな印象を受ける。
日本の感覚からすると、
一見、ぶっきらぼうに見える彼らだが、
実は、とてもプロ根性に徹しているのだね。
だから、効率よく、
そして実に、良心的な値段で、
一杯を楽しめる様になっているのだろう。
ああ、また、
スペインのバルで一杯やりたいなあ。
などと言いながらも、
とにかく、
目の前の難問と脅威に、、、。