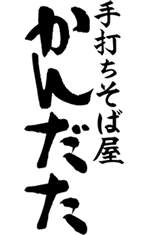久々にいただいたのは、
ホタルイカの沖漬け。
ついつい、私の苦手な、
お酒も進んでしまう。
ホタルイカの沖漬けは、
ともすれば臭みが出てしまうものだが、
ここのは美味しい。
土産物屋で売られている瓶詰は、
まったく別のものと考えて方がいいようだ。
こういう珍味を食べられるのは、
さすが富山県ならではのこと。
しかも、私達がいるのは、
海辺の食堂ではない。
標高2,450メートルにある、
立山は室堂にある山小屋なのだ。
観光客のあふれかえるバスターミナルから、
ゴツゴツとした岩の歩道を、
20分ほど歩かないとたどり着けない、
「みくりが池温泉」だ。
限られた設備の中で、
観光地にありがちな、
安易な食べ物を出さない姿勢に乾杯、、、
ではない、共感するところ。
なぜ、立山に行ったかといえば、
地元の観光会社の日帰りツアーに参加したのだ。
アルペンルートの室堂から、
湿原の弥陀ヶ原までを、
紅葉を楽しみながら歩いてみようと思ったのだ。
ところが、ところが、
案の定というか、
日頃の行いの悪い私達にこの天気。
仕方がないので、
山小屋で、飲み物研究会を開いたわけだ。
しかし、
この天気が幸いすることもある。
以前に来たときには見ることができなかった、
この鳥に会うことができたのだ。
そう、天然記念物の雷鳥。
こういう天気の悪い時に、
出てくることが多いという。
平気で人のそばまで寄ってきて、
挙句の果てに、杭の上に登って、
写真のポーズまでとってくれるのだから。
そんなことで、
忙しい中、思い切って行った日帰りツアーだったが、
なかなかの収穫があった。
往復のバスの中では、
日頃の寝不足解消とばかり、
寝てばかりいたが。
いや、一番書きたかったのは、
この観光会社のこと。
小さな会社なのだが、
こういうバスツアーをたくさん企画している。
それがねえ、なかなか、きめ細やかなサービスをしているのだ。
詳しくは書かないが、
なるほど、リピーターの多いことが頷ける。
特に女性には人気のようだ。
つい先日も、
この時に参加者でとった写真が送られてきた。
こういう気の回ることが、
今の商売に、大切なこと。
お客様の気持に沿った気遣いを、
何気なくすること、
そういう積み重ねが大切なのだね。
と、ちっとも気の回らない、
私達も、少しは考えたの、、、、、、だ。