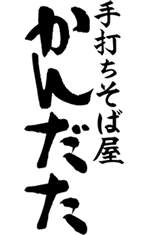●秋の味覚といわれる、松茸。
みなさん、今年は何回松茸をお食べになりましたか。
私なんかもう、数十回も、、、夢の中で、、、、
ということで、実物は一度も。
採れたての松茸は、火にあぶって、
熱いところを手で裂いて食べる。
これが最高。
こりこりとした歯ごたえが、たまらない。
でも、昨年は松茸の採れ高日本一になった長野県でも、
ちょっと、手に入れるのは難しい高嶺の花。
さあ、そばにも、その松茸を使ったものがあるようで。
東京の老舗のそば屋さんのお品書きの中に、
「おかめ」というのがある。
これは、暖かいそばの上に、
様々な具をのせてある、
ちょっと、贅沢な気分のそばだ。
「おかめ」とは、
下ぶくれの女性の顔のこと。
「お多福(おたふく)」ともよばれ、
縁起がいいと言われている。
様々な具を使って、
この「おかめ」の愛嬌ある顔を、
そばの上に描き出そうというのが、
この種物の特徴だ。
●この「おかめ」というそばを考案したのは、
江戸は入谷にあった太田庵というそば屋だった。
時代は幕末というから、
ちょうど「篤姫」が大奥にいた頃なのかもしれない。
具の並べ方は、
まず、一番上に、娘の髪型になぞらえて、
真ん中を結んだリボン状の島田湯葉を置く。
そうして、かまぼこを二枚、
下ぶくれの頬に見えるようにハの字に置く。
そのかまぼこの間に、
薄切りにした松茸を置いて、鼻に見立てる。
これを基本にして、
卵焼きを口にしたり、
椎茸や、小松菜、海藻などを髪の飾りに使ったり、
などと、いろいろと工夫がされたみたいだ。
それを蓋付きのどんぶりに盛り付け、
蓋を開けたとたん、
愛嬌のある「おかめ」の顔が現れるという趣向。
これが「見立て」を楽しむ江戸っ子たちの間で大受け。
それまで、具をのせたそばとして流行っていた、
「しっぽく」の影を、
瞬く間に薄いものにしてしまったそうだ。
●しかしながらこの「おかめ」。
今では、「おかめ」の顔をかたどって出されるところは、
ほとんどなくなった。
「おかめ」といえば、かまぼこと椎茸と青菜などを、
熱いそばの上に載せたものとなった。
肴の少ないそば屋では、
この「おかめ」を頼んで、
上に乗った具で、酒をちびちびと飲み、
最後に伸びきったそばを食べる、
という飲んべえも居るようだ。
さて、今回の話の中心は、
この「おかめ」の顔の中心にあるべきもの、
鼻に見立てたという松茸なのだ。
●松茸を具に使うということで、この「おかめ」
当初は、秋の限定メニューだったらしい。
ところが、そのうちに、
塩漬けの松茸が出回り、
一年を通して、出されるメニューとなった。
でも、松茸をつかうなんて、
かなり高級なそばだったんじゃないの。
ところがところが、
昔は、松茸というのは、
高級どころか、ごく、ありふれたキノコだったらしい。
その辺りの山でも、普通に採れていたキノコだったようだ。
統計によると、
昭和の初め頃がピークで、
全国で、1万トンをこえる松茸が採れた年もあったらしい。
ちょっと待てよ、一万トンというと、
一本50グラムぐらいの松茸に換算すると、、
約2億本。
国民一人当たり、二本ぐらいの松茸が食べれたのだ。
つまり、それほど珍しいものでもなかったのだね。
「おかめ」を作った太田庵。
当時としては、ごく、身近なキノコを、
使っただけなのかもしれない。
●先日、ある温泉施設に行ったら、
「松茸そば 800円」とある。
頼んでみたら、普通のかけそばの上に、
よく、これだけ薄く切ったと感心するぐらいの、
しかも小さな松茸が三切れ載っている。
それでも、松茸の香りはするのだ。
その周辺は松茸の産地だけれども、
多分、そばの上に載っていたのは、
外国産に違いない。
それもそのはず、国内の松茸の消費量の、
97パーセントは、中国やカナダなどからの、
輸入品だそうだ。
今や、国産の松茸は、
年に50トンぐらいしか採れないという。
松茸の入った「おかめ」そばを、
食べてみたい気がするが、
値段を見るのが、ちと、怖い。
かといって、「おかめ」の鼻が無いのも、
寂しいものだ。
それならば、栽培されて、広く出回っているシメジを使って、
新しいメニューでも考えようか。
「ひょっとこ」なんてね。
そばコラム
やせた土地でできる大根が辛い
●松尾芭蕉といえば、
江戸時代の有名な人。
そう、俳句を作っていた人だ。
その人が、故郷の伊賀を出て、
信州に旅をした。
その紀行文が「更科紀行」。
今から300年以上も前の話。
旅は、かなり難儀であったようだ。
善光寺にも寄ったらしいが、
その頃は、今の本堂が建てられる、
ちょっと前のことだった。
さて、その中に、こんな句がある。
○身にしみて大根からし秋の風
はははっ、
芭蕉さん、ちょうど秋の終わり頃採れる、
長野の地大根の辛さに、
よっぽどまいったらしい。
なかなか、いい句がまとまらないと、
紀行の中でぼやいていながら、
しっかりと、この句を書き留めているのだから。
でも、この辛い大根、
どのようにして食べたのだろうか。
単なるご飯のおかずか。
今でもこの地に伝わる「おしぼりうどん」なのか。
はたまた、そばの薬味として食べたのだろうか。
芭蕉が信濃を旅したのは45歳の時。
東北を旅する「奥の細道」より、
すこし前のことだ。
その壮年期の芭蕉さんが口をつぼめた、
辛い大根って、どのようなもんだったのだろう。
●長野市から少し南に下った、
更級地方。
ここは、今でも、辛み大根の産地だ。
ここで採れる「ネズミ大根」と呼ばれる、
それこそ、ネズミの格好をしたちっぽけな大根を、
すりおろして、そのわずかな汁をぎゅっと絞る。
その、乳白色の汁で、そばやうどんを食べるのが、
昔からの流儀。
これが、ものすごく辛い。
私が長野に来たばかりの頃、
初めてこの汁で、うどんを食べた時、
しばし、固まってしまった。
たかが大根の辛さと、
たかをくくっていたからだ。
唐辛子のひりひりする辛さとは違う。
言わせてもらえば、
頭の皮が、ピンと引っ張られるような辛さなのだ。
おかげで、そばやうどんの味なんぞ、
分かったものではない。
でも、味噌をその汁に溶きながら、
つい、食べ進んでしまうのだ。
この大根、この地方の痩せた土地にしかできないらしい。
ほかの場所で育てても、この、
暴力的ともいえる辛みは、でないのだそうだ。
●信州だけでなく、
地方では、大根の絞り汁に、
味噌を溶いて、そばを食べるのが一般的だったという話。
これならば、わざわざ、出汁をとる手間もない。
雪深い北信濃では、
こんな風に昔から言われてきたという。
「一そば、二こたつ、三そべり」
農作業のできない、
雪に閉じ込められた冬は、
こたつに入り、
辛み大根の汁で味噌を溶いたつゆで、
新そばをすすり、うとうととしているのが、
一番の極楽だったそうだ。
こういう食べ方も、
見直されていいのかもしれない。
もちろん、こたつ付きでね。
●大根は、場所によって、
様々な種類が作られている。
今でこそ、青首大根しか見かけなくなったが、
本来は、その土地にあった大根が育てられていた。
その中に、更級のねずみ大根のような、
辛〜いものも、あるのだね。
そんな大根を使って有名なのは、
「越前おろしそば」。
ここで使われる大根も相当辛いらしい。
一度食べにいってみたいものだ。
「かんだた」の畑でも、
今年は信州地大根を育ててみた。
ねずみ大根ほどではないが、
ちょっとピリ辛。
私の細いそばには、
はたして、合うのだろうか。
ご希望の方はお試しを。
この辛い大根を食べれば、
芭蕉さんのような、
いい俳句がつくれるかなあ。
何気なくこなしている、ものの数え方
●さて、問題です。
寿司屋で、
「マグロ、1カン(貫)」
と頼めば、何個のすしが出てくるのだろう。
えっ最近は、「皿」でしか数えたことがないって?
外国人が日本語を学ぶ時に苦労することの一つが、
ものの数え方だという。
日本語では、数字の後に、
それにふさわしい言葉をつけて、
その数を表す。
例えば、子供三人、大人五人、
船が一艘、飛行機一機、
我が家に一台、となりに五台の自動車。
犬はワンワン二頭いて、猫は三匹昼寝中。
ウサギは五羽で跳ね回る。
花は一輪、木は一本、
バラを十本で一束にして、六ヶ所に送る。
それぞれに、ものによって、
また、その状況によって、
私たちは、数え言葉を選んでいるのだ。
紛らわしいことに、
同じ犬にしても、
抱きかかえられるような小さなものは、
「匹」と呼び、
大きい犬は「頭」と呼ぶ。
海で泳いでいる魚は「匹」で数えるが、
魚屋に並ぶと「尾」に変わる。
イカやカニは「杯」と呼ぶ。
などなど
いろいろな決まりがあるのだねえ。
●さて、そば屋の世界では、
どんな数え方をするのだろうか。
お客さまが、
「そばを一枚おくれ。」
といえば、
もりか、ざるか、冷たい盛ったそば。
「そばを一杯。」
といえば、かけか、丼に入ったそば、
ということになる。
だから、
「寒かったから、二杯立て続くに食べた。」
「盛りが少ないから、五枚ぐらいは食べられる。」
と聞けば、何を食べるのか想像ができる。
厨房では、
それぞれの注文を「一丁」と呼ぶらしいが、
私は、使わないなあ。
なお、店によっては、
「一人前」と頼むと、もりが二枚出てきて、
「一枚」と頼むと、本当に一枚しか出てこない、
複雑なところもある。
●栽培されたそばの実の「一粒」一粒は、
収穫されて袋に詰められる。
そうして「一俵」ごとに出荷される。
ちなみに、そばの「一俵」は45キロ。
米の60キロとは、ちょっと違うのだね。
大麦は50キロ、炭は15キロで「一俵」と呼ぶそうだから、
人のかつぎやすい大きさで、決まるのかもしれない。
それが、製粉所に行って、
粉にされて紙袋に入れられると、
「一袋(たい)」と呼ばれる。
そば粉の「一袋」は22キロ。
どういうわけか、そのような決まりになっている。
そうして、各店でそばにされて、
一人前ずつに分けられると、
「一玉(たま)」と呼ばれたりする。
そばの麺は「一本」と数え、
かんだたには、
「そばは八本ずつ食べる」
という決まりがある。
(あまり気にしなくてもいいけれど。)
乾麺の場合は、それを束ねて、
「一把(わ)」とか「一束(たば)」とか呼ばれる。
それが箱に入れば「一箱」、
袋に入れれば「一袋(ふくろ)」。
よく、土産物屋の店先で売られているやつだ。
●注文が
「ビールを一本」といえば瓶ビール、
「ビールを一杯」と言われれば生ビール。
箸は「一膳」、床に落として、片方だけだと「一本」。
おつまみは「一皿」「一品(しな)」。
店で座る椅子は、
脚が四本あっても「一脚(きゃく)」、
テーブルは「一卓(たく)」。
楊枝は「一本」、紙おしぼりは「一枚」、
メニューブックは「一冊」または「一部」。
座敷に上がって脱いだ靴は「一足」、
上着をかけるハンガーは「一本」。
壁にかかった絵は「一点」、
掛け軸だったら「一幅(ふく)」、
生け花が飾ってあれば「一鉢(はち)」
帰りに頼むタクシーは「一台」、
おっと、忘れちゃいけない、傘は「一本」。
勘定書は「一枚」、
ええっ、「一通」にするほどツケが溜まっている。
ということで、「一組」のお客さまが、
お帰りになった。
なるほどなあ、
知らず知らずのうちに、ずいぶんと、
ものを数える言葉を使い分けているのだ。
●さて、おそばの前に、
「ちょっと一杯」という方もいらっしゃる。
この「一杯」というのは、
不思議な一杯で、
たとえ、おかわりを重ねようとも、
いつまでも「一杯」なのだ。
「そば前に酒を四杯飲んだ。」
などというのは、
警察に尋問された時か、
馬鹿正直な人の日記に書かれるぐらいで、
たいていは、
「ちょっと一杯」で済まされる。
いくら飲んでも「一杯」。
これも、不思議なものの数え方だなあ。
ちなみに、寿司屋で
「マグロ、一貫(かん)」
と頼むと、老舗の店では二個出てくる。
ところが、スーパーなどで頼むと一個。
まぎらわしいなあ。
本来は、江戸時代の穴あき銭一貫分の大きさで、
そのままでは、大きくて食べにくいので、
二つに分けて出したのが、始まりだとか。
つまり、握り鮨2個で一貫ということ。
ところが、最近は、手巻き寿司の「巻」や、
「個」がなまったものとする考えがあり、
一個のすしをあらわす意味と、
混同されてきているようだ。
だから、確認した方が無難。
ところで、そば屋で、
「そば、一貫」と頼むと、
生そばで3.75kg、
かんだたの場合だと約30人分のそばが、
どかんと出てくるのでご注意を!
そば好きだった稲荷大明神
●古い時代から、人々の信仰を集める善光寺。
この善光寺は、
人間ばかりではなく、
動物にも、篤い信心を持つものもいたそうだ。
本堂の西側にある経蔵の横に立っている灯籠は、
「むじな灯籠」と呼ばれている。
なんでも、下総の国(今の千葉県)から、
はるばるとやってきたムジナが、
人間に姿を変え、この灯籠を寄進したのだそうだ。
ところが、このムジナ、
かねがねの念願だった、
善光寺へのお参りを済ませてほっとしたのだろう、
泊まった宿坊の風呂で、つい、シッポをだしてしまった。
つまり、ムジナの姿を現してしまったのだ。
大騒ぎとなってしまったので、
そのまま、姿をくらましてしまったとか。
これと似たような話が、
東京のお寺に伝わっている。
キツネが僧の姿となって仏法を学んでいたのだが、
あるとき、寝ている時についシッポを見せてしまい、
本性がばれてしまったという。
このキツネが大のそば好きだった、、
というから、話がややっこしい。
●さてさて、今から時代をさかのぼること四百年近く、
江戸時代は初めの頃のお話。
江戸は、小石川というところに、
傳通院(でんつういん)という、徳川家ゆかりのお寺があった。
このお寺では、たくさんの若い僧たちが修行していたのだが、
その中で、抜きん出て優秀な学僧が居た。
その名を澤蔵司(たくぞうす)といい、
僅か三年余りで、浄土宗の奥義を修得するまでになった。
ところが、ある日、寝ている時に、
シッポを出してしまったのだ。
キツネの姿を同僚に見つけられ、
逃げ出した澤蔵司。
その夜、寺の和尚の夢枕に立ち、
「余は稲荷大明神であるぞよ。」
と正体をあかすのだ。
学業を授かったお礼に、
稲荷として寺を守護するとのことで、
和尚は社を建立した。
それが、澤蔵司(たくぞうす)稲荷として
今でも広く信仰を集めているとのこと。
●稲荷大明神が化けていたという、この澤蔵司は、
大のそば好きであったそうだ。
毎日のように傳通院の門前にあるそば屋に通っては、
そばを手繰っていたという。
ところが、ところが、
さすがにキツネの化けたもの。
そば屋のお勘定が、
いつの間にか、木の葉に変わっているのだ。
不思議に思ったそば屋が、
澤蔵司の後をつけると、
境内の椋(むく)の木のあたりで姿を消してしまった。
あとで、その澤蔵司が稲荷大明神の仮の姿と気づいて、
それから毎日必ず、初そばを稲荷に供えるようにしたのだと。
そのそば屋は稲荷のご利益があったのか、
今でも続いていて、
「稲荷蕎麦」を名乗っている。
果たして400年前に、
今のようなそばが食べられていたかどうか、、、
などと言う野暮な突っ込みは無しとして、
そば好きだった澤蔵司を祀る稲荷をお参りし、
そばを手繰ってみるのも面白いかもしれない。
●かんだたの店も、本堂からは少し遠いが、
善光寺の表参道の近くのある。
ひょっとしたら、
人間に姿を変えた、
信心深いムジナやキツネが、
善光寺の阿弥陀様をお参りして、
帰りにそばを食べに寄っているかもしれない。
いまのところ、
お金が葉っぱに変わるようなことは、
起こったことはないけれどね。
一茶の詠んだそばの花
●長野では9月になると、
あちらこちらでそばの花が咲き始める。
最近は、赤い花もあるけれど、
一般的には白い花が、畑一面に咲くのだね。
山々を背景に、この花を見ると、
いかにも「そば処信州」という感じがするのだ。
さて、信州に生まれた有名な俳人の小林一茶。
若い時は江戸に暮らしたが、
晩年は信州に戻り、その暮らしに根ざした作品を残した。
一茶の俳句は、
それこそたくさんあるけれど、
その中で、そばの花にまつわる句を探してみよう。
●先ず、有名なのがこちら。
「そば時や月の信濃の善光寺」
「そば時」とは「そばの花の時」のこと。
月の光に照らされた、一面の白いそば畑と善光寺。
そんな信州の象徴的な風景を詠んだのだね。
「痩せ山に はつか咲けり 蕎麦の花」
そばの花は、実になるまで、
けっこう長い間咲いているから、
その様子を「はつか」と詠んだのだろう。
痩せ山とは、そば以外の作物ができないような土地なのだろうか。
● こんな句もある。
「信濃路やそばの白さもぞっとする」
あれあれ、今度は、
そばの花を「ぞっとする」白さだといっている。
確かに、そばの花の白さは際立っているけれど、
ぞっとするほどの白さなのだろうか。
一茶の暮らした柏原(今の信濃町)は、
長野県の一番北の新潟県境に近く、
たくさんの雪が降るところ。
50歳を過ぎてから故郷に戻ってきた一茶にとって、
この冬の暮らしは、たいへん厳しく感じられたようだ。
一面に白い花が咲くそば畑を見て、
ああ、また冬がやってくる、、、
ということを実感したのではないだろうか。
つまり、白いそばの花を見て、
つい雪を連想して「ぞっとする」ことになったという。
●今の世の中を見通したような句もある。
「国がらや田にも咲かせるそばの花」
そう、今の日本では、減反のあおりを受けて、
本来は稲を植えるべき田に、そばを植えているのだ。
というよりも、田で作られたそばの方が、
畑で作られるより多くなっているのが現実。
田の方が、機械で管理しやすいからね。
さすが一茶、200年後のことを、
しっかり予想していた、、、、、、はずがない。
じつは柏原では、標高が高いため、
その当時では、稲がよく育たなかった。
だから、仕方なしに田にそばを植えたのだね。
「国がら」というのは、そういう「米も満足に育たない山国」、
というような意味があるようだ。
●よく「そばの自慢はお里が知れる」という。
つまり、そばがたくさん穫れるところは、
逆に、米が穫れない貧しいところということ。
だから、うかつにそばの自慢をすると、
自分が貧しい土地の出身であることがばれてしまう、
ということになる。
それでも一茶は、それを承知で、
あえてそば自慢をしている。
「蕎麦国のたんを切りつつ月見かな」
江戸にいた時か、あるいはどこかへ行った時にだろうか、
月見の宴で、つい、蕎麦の自慢が飛び出してしまう。
たとえ貧しさを笑われても、
やはり、故郷はいとおしいものなのだね。
こんな句もある。
「そば所と人はいうなり赤とんぼ」
はたして「そば所」と呼ばれて褒められているものだろうか。
実は、そういう場所は、
厳しい生活という現実を背負っているわけだ。
そんなことを考えなくても、
この句は、白い蕎麦の花の上を、
赤とんぼが飛ぶという、
色彩豊かな秋の情景が目に浮かんでくるようだ。
●一茶という人は、継子(ままこ)でいじめられたり、
長い間遺産相続で争ったり、
子供達がみな幼くして亡くなるなど、
家庭的には不幸な生き方をしたそうだ。
でも、一度は江戸に出たとはいえど、
故郷をこよなく愛し続けたようだ。
「そばの花江戸のやつらがなに知って」
はははっ、いいなあ、好きだなあ、
こういう意地を張る一茶って。
同じそばの花を見ても、
きれいな句を作った芭蕉や蕪村とは、
全く違った目を持っていたんだね。
そんなそばの花が実を付けて、
さあ、新そばの季節。
一面に白い花の咲く、そば畑の風景を思い浮かべながら、
そばをお手繰りあれ。
花魁(おいらん)の好んだ辛いそば汁
●紀伊国屋文左衛門 といえば、
江戸時代中頃に活躍した材木商人。
大もうけをして、派手に遊んだという話が伝えられている。
当時遊ぶといえば、江戸の吉原。
ここにはきれいな女性が揃い、
おいしい食べ物が、豊富にあったそうだ。
文左衛門は、そのころ二千人の遊女がいたといわれる、
この吉原の門を閉めさせ、
つまり、貸し切りにして、小判をばらまき、
豪華に遊んだので「お大尽」として、
江戸中の人々の評判となったそうだ。
さて、この紀伊国屋文左衛門 と張り合ったのが、
同じく材木商の、奈良茂こと奈良屋茂左衛門。
この人も、ずいぶんと派手な遊びをしたという。
こんな話が残っている。
ある時、奈良茂は、お気に入りの花魁(おいらん)に、
そばを二枚届けさせた。
一緒にいた友人が、
「おいおい、二枚だけということはないだろう。
よし、俺が、この郭中の人に、そばを振るまってやるよ。」
そう言って、そば屋にそばを注文した。
ところが、そば屋は売り切れだという。
そこで、他のそば屋をあたって見るが、
どこも、そばはもう無いという。
実は奈良茂、
周りのそば屋のそばをすべて買い取り、
たった二枚だけを、花魁に届けたのだ。
つまり、
その日、江戸でそばを食べられたのは、
その花魁だけ、、、、
、、ということをしたんだね。
●吉原は、江戸にそばを広まらせた、
大切な場所の一つだったそうだ。
江戸で、はじめて「そば屋」が出来たのも、
この吉原なのだそうだ。
値段はべらぼうに高かったが、
新しいもの好きの人々に受けたらしい。
その後、
花魁の出世の行事などに、
そばを振る舞う習慣ができたりして、
江戸っ子の中にそばがしみ込んでいったわけだ。
さて、
吉原の三浦屋というところに、
几帳(きちょう)という花魁がいたそうだ。
この花魁、めっぽうそば好き。
そうして、この几帳のおかげで、
江戸のそば汁は辛くなったとか。
●この花魁、なかなか我がまま、
いや侠気のあった人だったそうだ。
店のものが、
「花魁、永田町の野田様のお座敷でお呼びです。」
と迎えに来ても、
「あの人は、イヤでありんす。」
と、自分の目に叶う客でないと、
断ってしまったそうだ。
それでも、気に入った客には、
いろいろと世話を焼くので、とても人気が高かったとか。
たいへんなそば好きで、ちょっと間があると、
すぐ、そばを手繰っていたという。
客がいろいろと贈り物をしようとすると、
着物以外はそばを贈ってくれと頼んだそうだ。
そうして、贈られたそばは、
店の他の女性達や、
働く下女下男にまで振る舞ったそうだ。
時には、身銭を払って、
同じように、そばを振る舞うこともあったとか。
年季明けの几帳の支払いは、
半分はそば屋へのものだったそうだ。
こういう気っぷの良さは、
「はり」があるといって、
「いき」とともに江戸っ子に好まれたとか。
●さて、この花魁の几帳。
そばを食べる時には、
辛い汁を好んだのだそうだ。
折しも、関東で作られるようになった醤油が、
江戸に広く出回るようになった時代らしい。
それまでの江戸では、「下りもの」と呼ばれていた、
関西から運ばれてくる醤油が上物とされていたという。
ところが几帳は関西の醤油で作った汁を好まなかった。
そして、
「そばを食べるには、辛い汁に限る。」
といって、関東の醤油で作った江戸汁を使った。
なにしろ、名の通った花魁が言うことなので、
それが江戸っ子の中にも広まっていったようだ。
かくして、そのころの江戸では、
辛い汁のことを、几帳の名を取って「几帳汁」とよんだそうだ。
●この人気の花魁を身請けしたのは、
最初に紹介した紀伊国屋文左衛門との話。
文左衛門は後年になって事業に失敗し、
最後は質素な暮らしの中にいたというので、
几帳ははたして、好きなそばを食べていられたのかは、
わからないのだ。
今でも東京の老舗のそば屋の汁は、
かなり辛めだ。
そんな辛い汁に当たった時には、
かって「はり」のある花魁がいたことを、
思い出してみたりしてみてはいかが。
そばは食われて殻を残す。
● さて、長野はもう稲刈りの季節。
田んぼでは、稲がたわわに実っている。
今年は、天候にも恵まれて、
おいしいお米がたくさん穫れそうだ。
ところが、その米を横取りしようとするものがいる。
そう、バタバタと集団で飛んでくる雀たち。
そのために、稲の上にネットを張ったり、
キラキラ光るものを吊るしたり、
はたまた、数分置きに鉄砲のような音を出す装置を仕掛けたり、
と、農家の人は工夫している。
古くからの方法だと、
「かかし」を立てて人が居るようにみせたりした。
今でも、いかにも手作りの「かかし」を、
見かけることがあって微笑ましい。
さて、やはり長野では、そばの実も、
まもなく収穫の季節を迎えようとしている。
葉が落ちて、黒っぽい茶色の実が、
点々と塊になって、茎にぶら下がっている。
こちらも、雀に食べられないように、
ネットをかけたり、「かかし」を立てたりしなくては、、、、
という光景は、そば畑では見かけない。
雀は、米には群がるけれど、
そばの実には、見向きもしないのだ。
●私の小さな畑でも、
春に、豆の種を蒔く時には要注意。
畝を作って、豆を一カ所に3粒ぐらいずつ蒔いていく。
そして、ふと、振り返って見ると、
いつの間に鳩が数羽来ていて、
蒔いたばかりの豆を掘り起こしているのだ。
あわてて、追い立てる。
だから、豆を蒔くのは、鳥たちの目が利かなくなる夕方。
そして、すぐに、ネットで覆っておく。
ところが、そばを蒔く時には、
そんな気遣いは不要。
昼間から堂々と蒔いたって、
鳩もカラスも寄って来ない。
残った蕎麦粒を畑の隅に置き忘れたって、
一週間経っても、何の変化もないのだから。
そばの実は、
鳥たちには、まったくの不人気なのだ。
●そばの実は、三角形の固い殻で包まれている。
これが本当に固い、しっかりとした殻なのだ。
この殻があることが、
鳥たちの興味を惹かない一つの原因なのかもしれない。
でも、あの悪食のカラスさえ突こうとしない、
そばの固い殻を、
われわれ人間は、剥いて食べている。
とはいえ、このそばの殻を剥くのは、
けっこう難しい作業。
今でこそ、機械がやってくれるけれど、
昔は大変だったようだ。
家庭などでは、皮を剥かずに、
そのまま石臼で挽いて、
フルイにかけて、粉にならない殻の部分を、
取り除いていたそうだ。
今でも、田舎そばと呼ばれるものには、
そのようにして作られた粉を使っているものもある。
●そういう粉はともかく、
殻を取り除いて、粉にするのが、
一般的なそばの作り方。
私たちが、どんどんとそばを食べると、
やはり、どんどんと、そばの殻の山ができることになる。
さあ、このそば殻の使い方と言えば、、、、、
皆さんご存知ですね。
固くて湿気を含まない、
しかも安価なので、
盛んに使われた。
そう「そば殻まくら」としてね。
一時期は人気で、
日本で食べられるそばの殻だけでは間に合わず、
そば殻だけ中国から輸入するということも、
あったそうだ。
それが、今では、
音がうるさい、手入れが悪いと虫がわく、
値が安いので、店が儲からない、、、、
などの理由で、
あまり使われなくなってしまったという。
私は今でも「そば殻まくら」を使っているけれどね。
適当な固さだし、
夏でも、涼しくて具合がいい。
けれども、あまり売られているところを、
見なくなってしまったのは確かだ。
かくして、毎日大量に出るそば殻の、
行く場がなくなってしまったのだ。
●かくして、その硬さから、
鳥たちのクチバシから、
実を守っていた、そばの殻は、
いまや、産業廃棄物扱いになってしまった。
動物の飼料にはならないし、
堆肥にするには、固くてなかなか分解しない。
それでも、一部には、
炭に加工されて、「くん炭」として、
畑の土壌改良に使われているという話だ。
また、果樹園などでは、そば殻を蒔いておくと、
雑草が出にくくなるといって、
一面に敷き詰めているところもある。
私の畑でも、
瓜やカボチャのつるの延びる場所にそば殻を蒔いている。
そんなふうに使われるのはごく僅か。
今や、厄介者となってしまったそばの殻。
ところがねえ、今まで栄養分はないとされていたそばの殻にも、
実と同じぐらいのルチンや有効成分が含まれていることが、
最近、分かったらしい。
そのうちに、このそば殻から、
「からだを元気にするサプリメント」などと言うものが作られ、
大々的に売り出され、ブームになる、、、、、、、かも。
こんな風評被害があった。
○「困ったなあ。」
そば屋の太兵衛さんが渋い顔をしている。
「困ったなあ。」
やはりそば屋仲間の弥太郎さんも、
同じように眉間にしわを寄せて、相づちを打っている。
「どうしたものだろう。」
がらんとした店の中を見回しながら、
太兵衛さんが言うと、
「さあ、どうしたものだろう。」
と、弥太郎さんも、生気のない顔で答える。
隣り合わせで張り合って、
そば屋をやっていた二人だが、
今日は顔を突き合わせて相談している。
それほど、深刻な事態が起こっているわけだ。
場所は江戸、
時は安永二年(1773)のことだから、
今から240年前のお話となる。
二軒のそば屋が張り合っていたので、
かえって江戸中の評判となり、
客の切れることのなかった二人の店だった。
それが、
どうしたことか、両方の店ともに、
客がまったく来なくなってしまったのだ。
天気の加減かなと、はじめは思っていたのだが、
それが十日も続くと、そうも言っていられない。
奉公人たちは、手持ち無沙汰で、
うろうろしているばかりだ。
○そこへ、ひょいと入ってきたのが、
近くの小間物屋のご隠居。
「いやあ、ここも閑だねえ。
いまは、どこのそば屋も、まったく人の気配がないねえ。」
そういって、そばを頼んで手繰りあげる。
「まったく、ひどい噂が立っちまったものだ。
私なんざ、いつ死んでも構わないから、
こうしてそばを食べていられるがね。」
と、ご隠居さん。
そう、江戸の町に、
そばには毒があるとの噂が立ってしまったのだ。
それは、こんなものだ。
ーー綿の実を作った跡の畑で採れたそばに毒がある。
ーーそれを食べて死んだ人がいる。
ーー毒のあるのは、綿畑で作られてそばだが、それかどうかは、俺たちには判らない。
ーーだから、そばは食べない方がいい。
この噂は町中に広まり、
そばは、まったく食べられなくなってしまったのだ。
「それではこうしましょうか。」
太兵衛さんが切り出す。
「表に『綿畑で採れたそばは使っておりません』と、
張り紙を出しましょうか。」
弥太郎さんもそれがいい、ということで、
二店揃って、店先に張り紙をだした。
それでも、一向に効き目はなかったという。
ところが、「人の噂も七十五日」という言葉がある。
太兵衛さんと弥太郎さんが、「困った、困った。」を繰り返しているうちに、
ぼちぼちと、そばを食べる人が出てきた。
そして、三ヵ月もすると、
元の通りの繁盛となった。
ああ、よかったと、
胸を撫で下ろしたそば屋の太兵衛さんと弥太郎さん。
根拠のない噂は、
やっぱり、根を張らないものなのだ。
ところが、この噂、このままでは終わらなかったのだ、、、、。
○「困ったなあ。」
太兵衛さんの孫の小兵衛さんが渋い顔をしている。
「困ったなあ。」
そば屋仲間の、弥太郎さんの孫の弥三郎さんも、
眉間にしわを寄せている。
時は文化十年(1813)。
そば屋が、あらぬ噂に惑わされたその時から、
もう40年も経っている。
隣同士で張り合っていた二軒のそば屋は、
双方とも孫の代となっていた。
そして、またもや、
そばに毒があるという噂が、
江戸の町に広まったのだ。
そして、そば屋に客が寄り付かなくなった。
今度の噂はこんなものだ。
ーー田螺(たにし)の肥やしで栽培したそばに大毒がある。
ーーそのそばを食べて死んだ人が何人もいる。
ーーどれが田螺の肥やしで作ったそばか判らない。
ーーだから、そばは食べない方がいい。
「田螺というのは、田んぼにいるものだなあ。
田で作られたそばは、
山の畑で作られたそばに比べて味が落ちる。
それをこじつけて、誰かがこんな噂を流したのではないかね。」
太兵衛さんは弥三郎さんにそう言う。
「そうだ、そうだ、そうに違いない。
でも、困ったものだ。」
○そこへ、ひょいと入ってきたのが、
近くの小間物屋のご隠居。
「いやあ、ここも閑だねえ。
いまは、どこのそば屋も、まったく人の気配がないねえ。」
そう言って、そばを頼んで手繰りあげる。
「そう言えば、じい様が言っていたっけ。
昔も、そばに毒があるという噂が流れて、
そば屋さんは大いに困ったそうだ。
ところが、三ヶ月もすれば、そんな噂も忘れられて、
元に戻ったって。」
そのご隠居の言葉に、
顔を見合わせる小兵衛と弥三郎。
そう、そんな話を、
若い頃にじい様から聞いたことがある。
それではと、
「田螺(たにし)の肥やしで使ったそばは、
扱っておりません。」
と張り紙を出して、じっと我慢することにした。
ところが、
この時は、
二ヶ月経っても、
三ヶ月経っても、
そば屋に客は戻らなかった。
ついには、奉公人に暇を出し、
店仕舞いしたり、休業するそば屋が出始めたのだ。
これには奉行所も動き出した。
江戸の有名な医者に、
そばに毒がある根拠を問いただしたが、
医者は返事が出来なかったそうだ。
どのような内容か判らないが、
奉行所が「町触」を出したというから、
お上も放っておけなかったのだろう。
しかし、やっぱり人の噂である。
やがて「新そば」の張り紙がかかる頃になって、
ぽつりぽつりと、お客の姿が見えるようになった。
年の暮れになると、
威勢のいい江戸っ子の啖呵(たんか)が、
店の中を飛び回るようになった。
その姿を見て、
ほっと、胸を撫で下ろした小兵衛と弥三郎。
年が明ければ、
前の年の噂はどこへやら、
すっかり、元の通り、そば屋は繁盛したという。
この噂の真相は、
はっきりと判らないまま、
どこかへ消えてしまったようだ。
○情報の少なかった江戸時代、
今から200年前ごろは、
こんな噂で、そば屋は苦労をしていたのだねえ。
情報の発達した今の世の中では、
こんなことは、
まさか、、、、、、、
起こりませんよね?
いや、そうとも言えないかも。
どんな時でも、
胸を張って安心だといえるような、
そんな「そば」を作っていかなくては。
宮本武蔵はそばを食べたか?
○宮本武蔵は二刀流を生み出した、
江戸時代の初めの剣豪。
その生涯は吉川英治の書いた長編小説「宮本武蔵」で、
詳しく描かれている。
この小説は、過去に何度も映画やドラマになり、
広く知られている。
またまた、人気タレントを使って、
新しくドラマになるという話もあるようだ。
この小説の中で、
武蔵がそばを食べるシーンがある。
江戸の旅館で、
そばを食べるのだが、
その時に、そばに集まってくるハエを、
箸でつまんで取り除いていたという。
えっ、動いているハエを!
ちょうど、武蔵に文句を付けようととしていた隣の部屋の男が、
その様子を見て、
黙って引き上げていったというのだ。
なるほど、
剣豪として研ぎすまされた動きが、
こういうところにも表れるのだ。
○この吉川英治の小説が新聞に掲載されたのが、
昭和10年という。
長い物語なので、何年かにわたって連載されたそうだ。
ところがこの小説に噛み付いた、
江戸文化の研究家が居た。
その名を三田村鳶魚(えんぎょ)という。
この人は、
江戸時代を舞台にした、
様々な小説について、
時代考証をして意見を言っていた人なのだ。
三田村の言うことには、
武蔵が活躍したこの時代には、
今食べられているようなそばは、
まだなかったという。
だから、
この、武蔵がそばにたかるハエを箸で捕まえたという、
良く引用される有名なエピソードは、
あり得ない話なのだそうだ。
○ソバの栽培は、
五世紀ぐらいから行われたらしい。
でも、それが粉になり、
さらに、長い麺に作られた、
つまり「そば切り」になって広まったのは、
江戸時代中期になってからといわれる。
年代でいうと1700年前後のお話。
今から約三百年前のこと。
ちょうどその頃、
関東でも醤油が造られるようになり、
さかんに出回るようになった。
そうして、その醤油の汁で食べる「そば切り」が、
江戸で人気になったわけだ。
さて、宮本武蔵が江戸でそばを食べたのは、
推定すると1620年頃。
三田村が調べた文献では、
そばが初めて現われるのは、
それより半世紀も後のこと。
だから、
宮本武蔵が、そばを食べたというのは、
へそが茶を沸かすようなもんだ、、、というのだ。
○そうか、宮本武蔵は、
そばを食べることはなかったのだ。
ところがどっこい、
これは小説「宮本武蔵」が発表され、
それに三田村が噛み付いた、昭和の初めのお話。
戦後になって、さらに、
そばの歴史の研究が進んだ。
そして、なんと、
宮本武蔵と同年代、
1620年頃に、「そば切り」を食べたという記録が、
ある僧侶の日記の中にあることが分かったのだ。
特に珍しいという感じではないので、
すでに、知られている食べ物だったようだ。
さらに、
長野県の木曽のお寺では、
1574年に「そば切り」を振る舞ったという記録が発見される。
ということは、
ひょっとしたら、宮本武蔵はそばを食べたかもしれないのだ。
少なくとも、
三田村のように頭から否定することは出来ないのだね。
○さて、真実はともあれ、
小説には小説ならでの面白さがあって、
これは、宮本武蔵のすごさを描いたもの。
私も、箸でハエを捕まえる練習でも始めることにしよう。
石臼ゴロゴロ
◯「そばほど贅沢な食べ物はないですよ。」
そばの製粉の機械を作っている方が、こうおっしゃっている。
「これだけ食べるのに、手がかかる食べ物は、
まず、他にはないでしょう。」
そう、 そば畑から、そば屋のせいろに盛られるまで、
そばは、実にたくさんの手数を掛けられているのだ。
そば屋だって、粉から麺にするまで、
ずいぶんと時間と手間がかかる。
特に、私のような手打ちの場合は、
なおさら体を働かせなければならない。
だけど本当は、その前の仕事、
そばの実から粉にするまでのほうが、
はるかに手間と時間がかかっているのだ。
確かに、製粉屋さんに行けば、
いろいろな機械がゴトゴトブーンと動いている。
そばの実を磨く機械や、石を取り除く装置、
実の大きさを揃える、皮をむく、
そばの実を選別する、実を割る、
臼(うす)で挽く、ふるいに掛ける、
それを混合する、袋に入れる、
実に、たくさんの種類の機械が働いているのだ。
これらの機械を作る方は、
さぞかし、苦労と工夫を重ねてこられたのだろう。
だから、最初の言葉のようになったのだね。
◯さて、今では、臼(うす)で粉を挽く、
そして、その前後の細かい作業を、
すべて、電動式の機械がやってくれている。
でも、そんな機械のなかった時代には、
一体どうしていたのだろう?
人の手で臼を回していたのだね。
(まあ中には、脚で回す人も居たかもしれないが。)
臼は大抵、直径30センチから35センチぐらいの丸い石でできている。
そばをよく挽くことができるように、
かなりの重さがある。
それを、外側に付いている穴に、
木の股を使った棒でひっかけて、
ぐるぐると回すのだ。
これが、ちょっとコツがあり、
その棒を手の中で滑らせるようにして回すのだ。
ぎゅっと握って、力任せに回そうとすると、
棒は穴から外れてしまう。
上の穴から、少しずつ、
皮を剥いたそばの実を入れながら、
臼をゴロゴロと回し続けなければならない。
そうして、少しずつ、
少しずつ、、、、
本当に、情けないぐらい少しずつ、
そばの実が粉になって、上下の石の隙間から落ちてくるのだ。
◯ここ長野あたりでは、
昭和のはじめぐらいまで、
石臼は、嫁入り道具の一つだったという話を聞いたことがある。
信州は、女性が家庭でそば打ちをしていた。
日々の食事だけでなく、
婚礼などのハレの日にもそばが振る舞われ、
その家の主婦が、そばを打つのが当たり前になっていたようだ。
そばを打つには、まず、粉を挽かなければならない。
主婦は長い時間床に座り込んで、
ゴロゴロと、重い石臼を廻して、
家族の分のそば粉を挽いたのだ。
「そばを打つ日は、ばあさんが縁側に座って、
半日かけて石臼を廻していたっけなあ。」
などと、年配の方が、思い出話をしたりする。
なかには、
「学校から帰ると、粉挽きをやらされて、
嫌で嫌でたまらなかった。」
などという方も居る。
粉を挽くのは、
女性と子供の役割だったのだね。
○その家に娘が居ると、
その娘は、夜に次の日のそば粉を挽く習慣があったとか。
娘さんも大変だったね。
ところが、娘が夜に、
ため息をつきながら(本当にため息をついたかどうか知らないが)、
石臼を廻しているという話を聞くと、
近所の若い男たちが黙っていない。
機会をうかがっては、
石臼を廻すのを手伝うというのを口実に、
娘のもとに通う男も居たとか。
いつもは退屈な粉挽き仕事も、
二人で、あるいはもっと大勢で、
交代に臼を廻せば、
楽しい時間となったことだろう。
○さて、そばの大消費地であった江戸では、
どのように、そばを粉にしていたのだろう。
ここでは分業がかなり進んでいて、
水車を使って、そばの皮を取る、
専門の業者が居たという。
その業者が、江戸中のそば屋に、
丸抜き、つまり、皮をむいたそばの実を届けるのだ。
当時のそば屋には「臼場」という場所があり、
ここで、専門の職人が、
終日臼を廻して、そば粉を作ったという。
これも大変な仕事だっただろうなあ。
でも、動力の普及により、
そういう仕事も無くなっていったのだ。
○店で若い人に、石臼で挽いたそば粉を使っていると言ったら、
こう言われてしまった。
「臼って、正月のお餅をつく時に使うものでしょう。
へえ〜、それが石でできているんだ。」
あれっ、何か話が噛み合ないなあ。
もっとも、今の若い方は、
ぐるぐると廻る石臼なんぞ、
自分で廻したことはないし、
見たこともないのかもしれない。
そばの実からそば粉を作ることが、
どんなに大変なことなのかを知っていただくためにも、
どこかで、石臼をゴロゴロと廻すことが、
体験できる場所があるといいな、、、、
、、などと思ったりしている。